簿記3級を取りたいけど「ネット試験って難しそう…」「いつ申し込めばいいかわからない」そんな不安を抱えていませんか?
実は、ネット試験は一般の統一試験と同等の難易度でありながら、いつでも受験でき即座に結果がわかるため、最短合格への近道なんです。
この記事では、簿記3級ネット試験の日程から具体的な攻略法まで、簿記3級ネット試験で確実に合格するために必要な情報をお伝えします。読み終わる頃には「簿記3級を取得したい!」と思えるはずです。
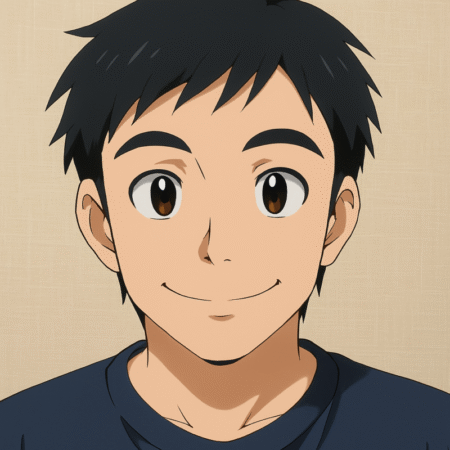
この記事の筆者:「うどまる」
沖縄出身。建設業とトラックドライバーを経て、2021年よりブロガー兼Webライターとして活動中。
簿記3級ネット試験とは?
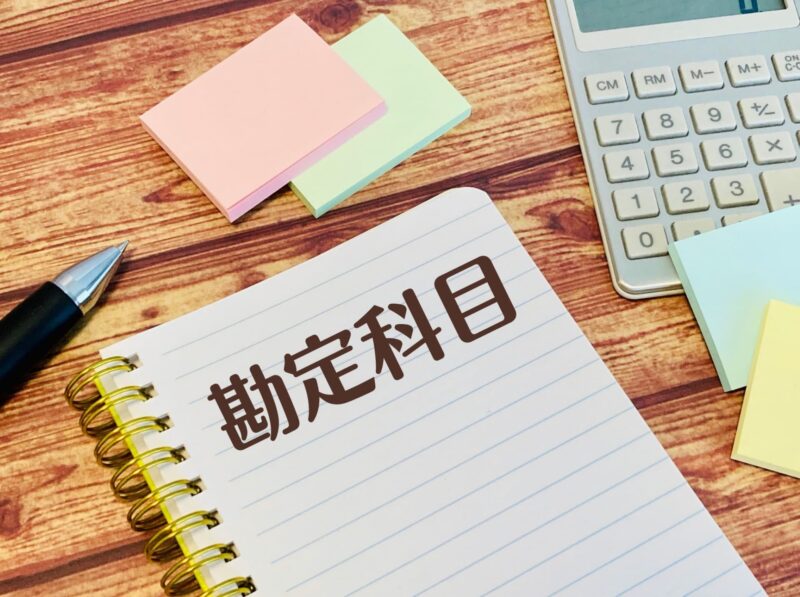
簿記3級のネット試験とは、パソコン上で受験(解答)することを指し、CBT(Computer Based Testing)試験とも呼ばれます。
パソコン上といっても自宅のパソコンでは受験できません。指定された試験会場へ行き、そこに設置されているパソコンで受験します。
簿記3級試験は、以前は統一試験(筆記試験)のみでしたが、新型コロナの対策として2020年12月よりネット試験が導入されました。
その後は統一試験と並行して実施していましたが、東京商工会議所では、2023年度から統一試験がなくなり、ネット試験のみでの受験になっています。
簿記3級ネット試験情報
試験時間や受験料などの基本的な部分は変わりませんが、ネット試験ができない日(施行休止期間)は必ずチェックしましょう。
基本情報
- 試験時間:60分
- 受験料:3,300円(+事務手数料550円)
- 合格基準:70点以上(100点満点)
- 出題形式:第1問(仕訳)、第2問(補助簿・勘定記入)、第3問(総合問題)
ネット試験施行休止期間
- 2月16日〜25日
- 4月1日〜13日
- 6月2日〜11日
- 11月10日〜19日
統一試験との比較|ネット試験が圧倒的に有利
統一試験は受験から合否が分かるまで約1か月待たされますが、ネット試験はパソコン上で受験するため、終了後すぐに合否が分かります。
なんでもそうですが、受験というのは合否が分かるまでドキドキと不安で落ち着かないものですよね。
そういう意味では、即座に結果の分かるネット試験の方が、次の対策や行動も取りやすいといえるでしょう。
| 項目 | ネット試験 | 統一試験 |
|---|---|---|
| 受験頻度 | 施行休止期間以外(約320日/年) | 年3回のみ |
| 合否発表 | 即日 | 約3週間後 |
| 再受験 | 最短3日後 | 最短4ヶ月後 |
| 会場 | 全国多数の試験会場 | 限定された会場 |
ネット試験が統一試験より有利な3つのメリット

近年、簿記に限らず多くの資格試験や検定でネット試験(CBT)の導入が進んでいますが、従来の統一試験と比べて、ネット試験には以下の3つのメリットがあります。
メリット1:自分のペースで学習&受験できる
統一試験が年3回のみなのに対し、簿記3級ネット試験は施行休止期間を除いてほぼ毎日受験可能です。
勉強が仕上がったタイミングで受験できるため、知識が新鮮な状態で本番に臨めます。
また、統一試験のように試験日に間に合わせなければというプレッシャーがなく、自分のペースで確実に実力をつけてから受験できます。
メリット2:即座の結果確認で時間ロスがない
試験終了後すぐに結果が分かるため、合格なら即座に次のステップ(2級、1級の学習)に取りかかれます。
統一試験のように合否が分かるまで数週間待たされることがないため、時間ロスが一切ありません。
また、資格取得後すぐに履歴書に記載できるため、就職や転職活動にも有利といえるでしょう。
メリット3:再受験は3日後から可能
不合格の場合、統一試験なら再受験できるのは4か月後ですが、ネット試験は最短3日後に再受験可能です。そのため、年に何回でもチャレンジできます。
合格率は概ね30%〜50%で、これはネット試験でも統一試験でも差はありません。同じ合格率なら、即座に合否が分かるネット試験を受験する方がメリットがあるといえるでしょう。
統一試験は合否結果も再受験もネット試験より待たされるため、短期間で取得したい方にはおすすめできません。
 筆者
筆者筆者は一度落ちたあと半年後に再受験し合格しました
ネット試験にデメリットはないの?
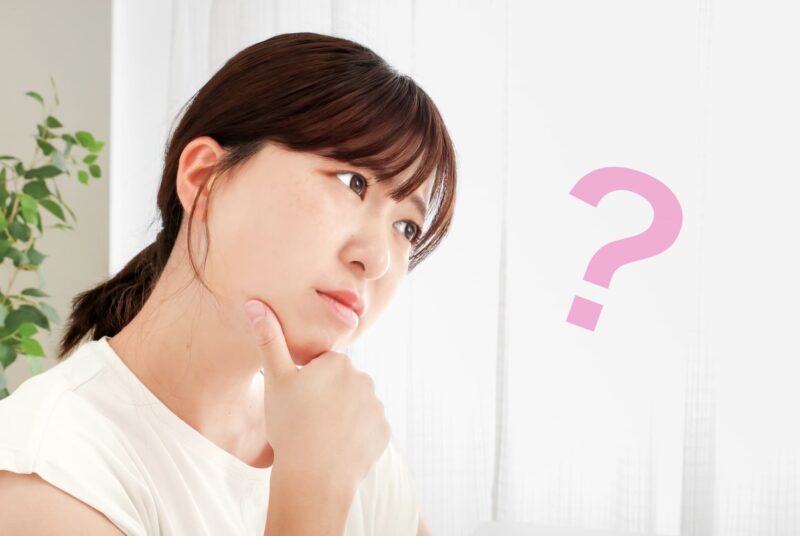
メリットだけが目立つネット試験ですが、あえてデメリットをあげるとしたら以下の2つが考えられます。
パソコン操作の慣れが必要
ネット試験はパソコン上で受験するため、パソコンを使ったことがない方にとってはハードルが高いかもしれません。
とはいえ、解答は勘定科目が選択式で、自分で入力するのは金額だけです。
そのため、基本的なマウス操作や数字入力ができれば、パソコンに詳しくなくても受験は可能です。
ただし、試験時間が60分と限られているため、ある程度キーボード入力に慣れておく必要はあります。
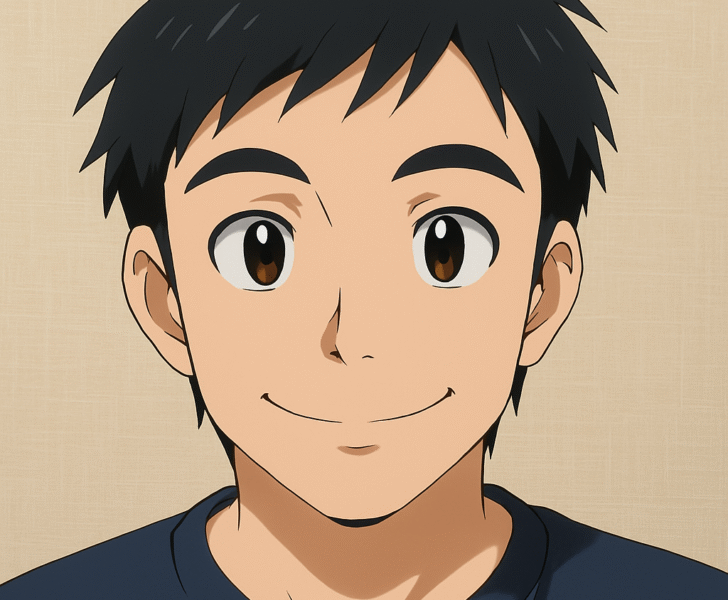 うどまる
うどまる「100,000円」→「10,000円」などの入力ミスに注意です
施行休止期間は受験できない
ネット試験は統一試験前後の約10日間(施行休止期間)は受験できません。そのため、この期間を避けて学習計画や受験日を調整する必要があります。
しかし逆にいえば、それ以外の日(約320日)はいつでも受験可能なので、大きなデメリットとはいえないでしょう。
ネット試験施行休止期間
- 2月16日〜25日
- 4月1日〜13日
- 6月2日〜11日
- 11月10日〜19日
最短合格するためのネット試験攻略法
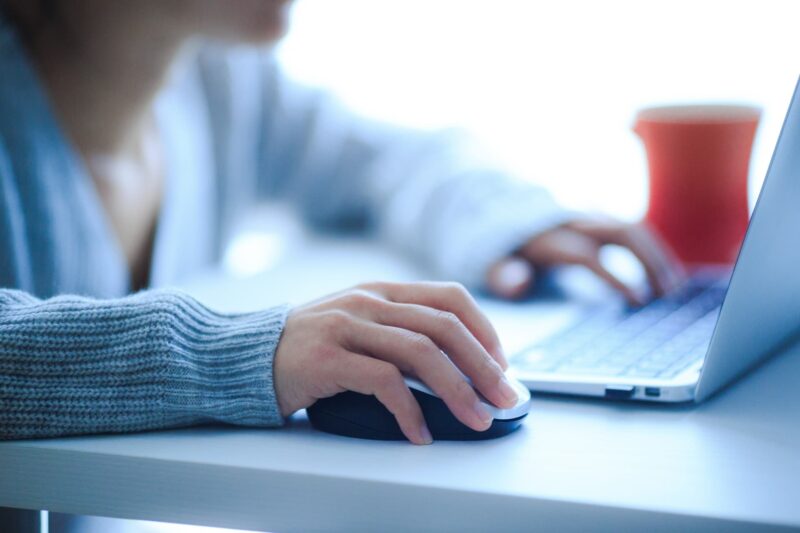
簿記3級ネット試験は自分のペースで学習でき、試験日の調整もしやすいので、統一試験よりも短期間で合格できます。
しかし、パソコン上で受験するネット試験は、筆記式の統一試験と異なる学習方法が必要です。
この章では、ネット試験で最短合格するための5つの攻略法を紹介します。
パソコン操作をマスターする
簿記3級のネット試験で最も重要な基礎スキルがパソコン操作です。画面上での仕訳選択や金額の入力など、紙の試験とは大きく異なる操作環境に慣れることが合格への第一歩となります。
特に入力ミスや操作に手間取ることで時間をロスしてしまうケースが多いため、事前の操作練習をしておくと安心です。
本格的な学習を始める前に、まずはネット試験特有の操作方法を確実にマスターしましょう。
効率的入力テクニック
- 金額入力:数字のみ(¥マークや余分なスペース禁止)
- 勘定科目:プルダウンメニューから素早く選択
- 画面移動:Tabキーでの効率的な移動をマスター
時間配分を考え得点を最大化
簿記3級ネット試験では限られた時間内で確実に得点を重ねる時間配分戦略が合否を左右します。
各問題の配点と難易度を見極め、解ける問題から優先的に取り組むことで、部分点を効率的に積み上げることが可能です。
特にネット試験では解答順序の調整ができるため、従来の順番通りに解く必要がありません。
確実に取れる問題を見落とすことなく、制限時間を最大限に活用する戦略的アプローチをマスターしましょう。
例えば、難しいと感じる人が多い第2問を最後にして、第1問の次は第3問を解いてもいいでしょう。
理想の時間配分
- 第1問(仕訳):15分 → 1問1分ペース、確実に満点狙い
- 第2問(補助簿・勘定記入):15分 → パターン問題、慌てず確実に
- 第3問(総合問題):25分 → 配点35点、最も重要な時間投資
- 見直し:5分 → 気になるところをチェック
計算用紙を活用する

ネット試験では試験前にA4サイズのメモ用紙が配布されます。この計算用紙をうまく使うことで正解率がグッと上がります。
仕訳を紙に書いて整理したり、試算表の計算を書き出したり、勘定科目をメモしたりと、頭だけで考えるより紙に書いた方が断然ミスが減ります。
パソコンで解答する都合上、画面にメモをすることができないため、紙のメモ用紙を有効に使いましょう。
仕訳下書きの徹底
画面の問題文を読んでも、必ず計算用紙に仕訳を下書きしてから入力するのがおすすめ。この一手間で、入力ミスを劇的に減らせます。
第3問専用レイアウト
決算整理では計算用紙に簡易的な整理表を作成するのもおすすめです。
見直し時に計算過程を確認でき、部分点も確実に獲得できます。
ネット試験特有の攻略ポイント
簿記3級のネット試験には紙の試験にはない独特の特徴があります。
まず画面表示をうまく活用することが大切です。長い問題文が出てきたら、重要なポイントを計算用紙にメモしながら読み進めましょう。
また、画面をスクロールして最後まで確認し、見落としを防ぐことも重要です。
操作ミスを防ぐためには、入力した後に必ず画面で内容をチェックする習慣をつけましょう。
プルダウンメニューで勘定科目を選んだ時も、本当に正しい科目を選んでいるか再確認が必要です。
また、数値を入力する際は桁数に注意し、凡ミスがないように注意しましょう。
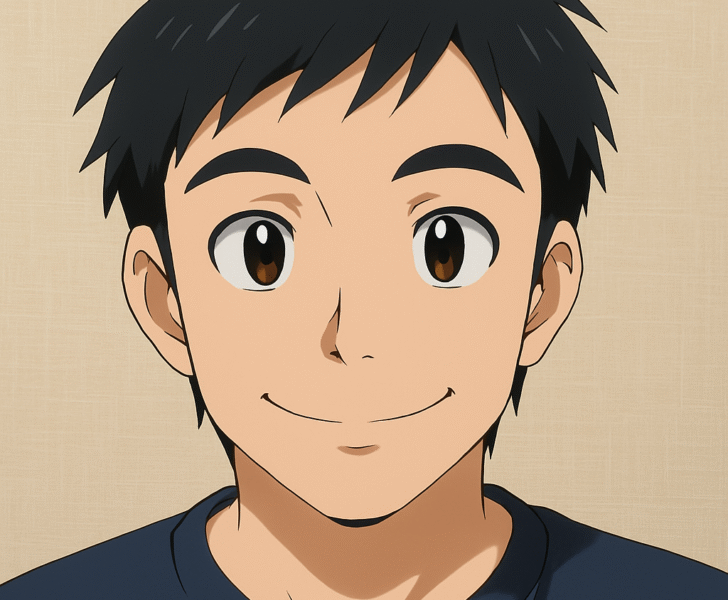 うどまる
うどまるプルダウンの選択と金額間違いはよくあるミスなので注意です
模擬試験での実戦練習が成功の鍵
本番で実力を発揮するには、模擬試験での実戦練習が欠かせません。ネット試験は紙の試験とは全く違う環境なので、どれだけ知識があってもパソコン操作に慣れていないと思わぬところで時間をロスしてしまいます。
模擬試験を繰り返すことで、本番と同じ画面操作や時間配分に自然と慣れることができます。特に「この問題にはどのくらい時間をかけるべきか」「どの順番で解くのが効率的か」といった感覚は、実際に画面で練習しないと身につきません。
また、間違えた問題や時間がかかりすぎた問題を理解することで、本番までに重点的に復習すべきポイントが明確になります。
可能な限り本番に近い環境で練習を重ね、当日は落ち着いて実力を発揮しましょう。
簿記3級の効率的な勉強法

簿記3級は正しい学習法を実践すれば、短期間での合格も十分可能です。
実際に多くの受験者が2-3ヶ月の学習で合格を果たしており、独学でも十分に対応できる試験です。
ここでは、効率的な学習ステップと教材選択のコツをご紹介します。
2-3ヶ月で合格する学習ステップ
短期集中で合格を目指すには、段階的な学習計画が重要です。
以下の3ステップで着実に実力を積み上げましょう。
Step1:基礎固め(2-3週間)
簿記学習の土台となる重要な期間です。まず資産・負債・純資産・収益・費用の5要素と「借方=貸方」の複式簿記原理を理解します。
次に現金、売掛金、買掛金、商品、売上、仕入などの主要勘定科目を確実に暗記しましょう。
勘定科目は簿記の「単語」であり、曖昧にすると後の学習に支障をきたします。
最後に現金取引、商品売買、掛取引の基本仕訳パターンを反復練習し、条件反射的に仕訳できるレベルまで習熟させることが目標です。
Step2:問題演習(3-4週間)
基礎力を実戦力に変える重要な段階です。1日20-30問の仕訳問題を継続的に解き、様々なパターンに慣れましょう。
間違えた問題は必ずテキストや動画を見かえし、原因を分析することが大切です。
同時に現金出納帳、売掛金元帳などの補助簿作成と総勘定元帳への転記練習を行い、帳簿間の関連性を理解します。
さらに減価償却、貸倒引当金、売上原価算定などの決算整理仕訳を学習し、配点の高い分野を確実に得点できるよう計算過程を丁寧に確認する習慣をつけます。
Step3:総合対策(2-3週間)
本試験に向けた最終調整の期間です。過去問や予想問題を60分の制限時間内で解き、時間配分や問題の取り組み順序などの実戦的な戦略を身につけます。
特にCBT形式の模擬試験で電卓操作、画面の見方、入力方法など、ネット試験特有の操作に慣れることが重要です。
模擬試験の結果から弱点分野を特定し、集中的な復習を行います。
苦手分野を放置せず確実に克服することで、本番での得点力を最大化できます。この段階では知識の補強よりも実戦感覚の養成に重点を置きましょう。
教材選択のポイント

教材選びは学習効率に大きく影響します。
簿記3級ネット試験を受ける場合、それに対応した教材を選択することが重要です。
ネット試験対応教材の条件
動画:CBT(ネット試験)対応のものを視聴し、実際の試験画面に近い形で学習できる環境を整えます。
テキスト:図解やイラストが豊富で視覚的に理解できる教材を選ぶ。
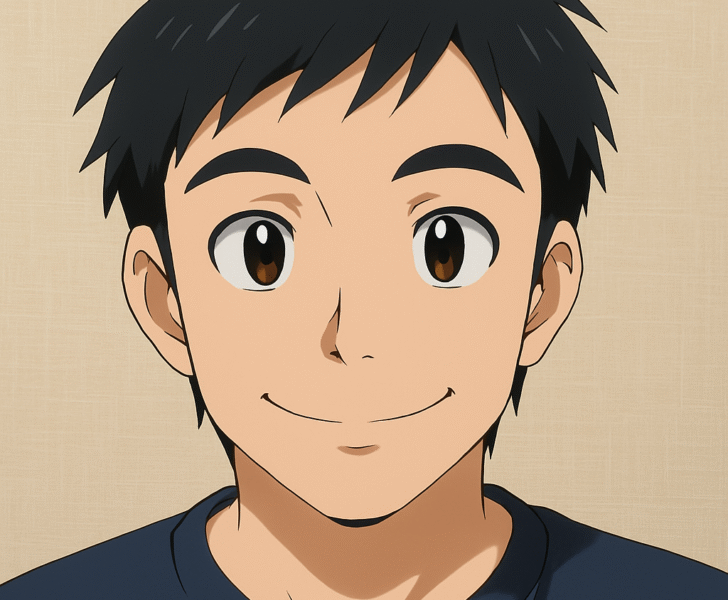 うどまる
うどまるなるべく最新のものを選択することも大事です
無料学習サイトを活用する
問題集のような冊子を購入して学習するのもいいですが、ネットの無料学習サイトを活用するのもおすすめです。
たとえばYouTubeでは、簿記3級に関する解説動画が数多く公開されており、仕訳の考え方や計算過程を視覚的に理解できます。
また、経理実務学校やCPAラーニングなどのサイトでは無料で簿記3級の受講が可能です。
テキストと動画を組み合わせれば、より効率的な学習ができます。
無料で学べる動画サイト
経理実務学校公式サイト
独学でも合格できる理由
簿記検定は独学でも十分に合格可能な試験です。その理由は出題範囲が明確で、学習すべき内容が体系化されているからです。
簿記は論理的な思考に基づく学問であり、基本的なルールを理解すれば応用問題にも対応できます。
また、多くの良質な教材や無料リソースが充実しているため、独学でも質の高い学習が可能です。
重要なのは毎日少しずつでも学習を続け、わからない部分は放置せずに確実に理解することです。
そうすることで着実に実力を向上させることができます。
申込から受験当日までの完全ガイド

試験に挑むまえに、ネット試験の申し込みから受験までのステップを理解しておきましょう。
申込方法は2つから選択
CBTSサイトからのネット申込
- CBT-Solutionsの専用サイトで会員登録
- 受験地・日時を選択
- クレジットカード、コンビニ、Pay-easy決済で支払い
- 確認メールを受信・保存
会場問い合わせ方式
各テストセンターに直接電話で申込(会場によって手数料が異なる場合があります)。
簿記3級ネット試験費用:3,850円(受験料+手数料)
申込時の注意点
ネット試験の申し込みは基本的にオンラインで完結しますが、受験できない日(施行休止期間)やキャンセル時の対応などは事前に確認しておきましょう。
また、受験には身分証明書が必須ですので、絶対に忘れないようにしましょう(受験可能な身分証明書はこちら)。
電卓は持ち込みOKですが、関数電卓など一部持ち込み不可のものもあるため、注意が必要です(持ち込み禁止の電卓はこちら)。
受験当日の持ち物
受験当日は、会場に行く前に必ず持ち物を確認しましょう。
特に身分証明書を忘れてしまうと受験できません。せっかくこの日に備えて学習してきた意味がなくなってしまうので絶対忘れないようにしましょう。
電卓は一般的な四則計算(+、−、×、÷)のみ可能なものしか使えません。スマートフォンや腕時計の電卓機能や、関数電卓は持ち込みできないので注意しましょう。
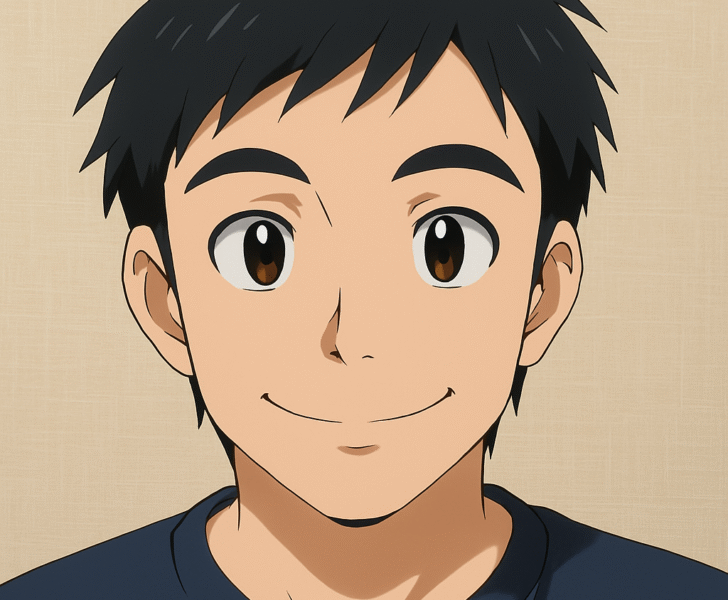 うどまる
うどまる電卓を忘れたら会場で提供される計算用紙に手書きで計算するのもあり
必須の持ち物
・身分証明書:運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等(写真付き・有効期限内)
・電卓:四則演算のみ可能なもの(関数計算機能、辞書機能、スマホの電卓は不可)
会場で提供されるもの
・筆記用具(ボールペン)
・計算用紙(A4サイズ2枚)※試験後に回収
・耳栓(会場により提供なしの場合有り)
試験会場入場→試験
試験開始30分〜15分前に会場に入るようにしましょう。それ以後は試験終了10分前までは受験可能ですが、試験時間は延長されません。
会場では「受験ログイン情報シート」と計算用紙、筆記用具が渡されます。
席に座ったら受験ログイン情報シートに記載しているIDとパスワードをパソコンの画面に入力して試験スタートです。
試験時間は60分で、画面下に経過時間がカウントされます。このカウンターを目安に、第1問〜第3問を上手く時間配分して解いていきましょう。
試験中は試験に関する質問は一切できません。ただし、パソコンに何らかのトラブルがあった場合はすみやかに試験管に報告してください。
試験の流れ
- 試験開始30分前から受付開始
- 10分前までに受付完了必須
- 身分証確認後、荷物をロッカーに預ける(スマホ、腕時計持ち込み禁止)
- 計算用紙と筆記用具を受け取り入室
- パソコンにID・パスワード入力で試験開始
- パソコンに不具合が発生したときは、試験管に報告し対応してもらう
- 試験終了後、合否確認とスコアレポート受領
結果はその場で分かる
試験時間は60分ですが、時間を待たず、回答が終わり次第終了することも可能です。
そのときは画面上の終了ボタンをクリックすると合否の判定結果が表示されます。
60分になると自動的に終了となり、合否の判定がでたら試験管に声をかけるか、席を離れてください。
試験管に筆記用具と計算用紙を返却し、試験結果(A4紙)を受け取ります。
試験結果は合否に関わらず渡され、合格した場合は用紙に合格証発行のコードが表示されるので、自分のスマートフォンで読み取り、デジタル合格証を発行してください。
ネット試験ではデジタル合格証のみが発行され、紙の合格証はもらえません。そのため、紙の合格証が欲しい場合は、統一試験(筆記用具)を受けることになります。
簿記3級ネット試験に関するよくある質問

Q. 本当にパソコン操作は難しくない?
A. ネット試験では基本的に数字(金額)を入力するため、数字キーを入力とマウス操作ができれば問題ありません。心配な方は事前に入力の練習をしておきましょう。。
Q. 電卓はどのタイプを準備すべき?
A. 四則演算(+、-、×、÷)ができる一般的な電卓で十分。関数計算機能や辞書機能付きは使用禁止です。価格は1,000円程度のベーシックなもので問題ありません。
Q. 試験中にシステムトラブルが起きたら?
A. すぐに試験官に報告してください。別端末での継続受験や別日程での受験が保証されており、不利益を被ることはありません。
Q. デジタル合格証の信頼性は?
A. 統一試験と完全に同等の価値があります。QRコードによる認証システムで、むしろ偽造リスクは低く、企業の人事担当者からも高く評価されています。
Q. 不合格の場合、どのくらいで再受験できる?
A. 試験翌日から3日後以降に再受験可能。同一会場での連続受験に制限がある場合もありますが、近隣の別会場を利用すれば問題ありません。
簿記3級は取って損しない資格。さらに上を目指すのもおすすめ

簿記3級に合格すると就職活動はもちろん、すでに勤務中の方でも会社の経理でその知識が活かせます。
そして、さらに簿記の知識を深めたい方や公認会計士を目指す方には、2級や1級を受験するのもおすすめです。
簿記はとても難しい資格ですが、3級を合格して少しでも簿記が楽しい!と感じた方は、2級や1級を目指してみてはいかがでしょうか。
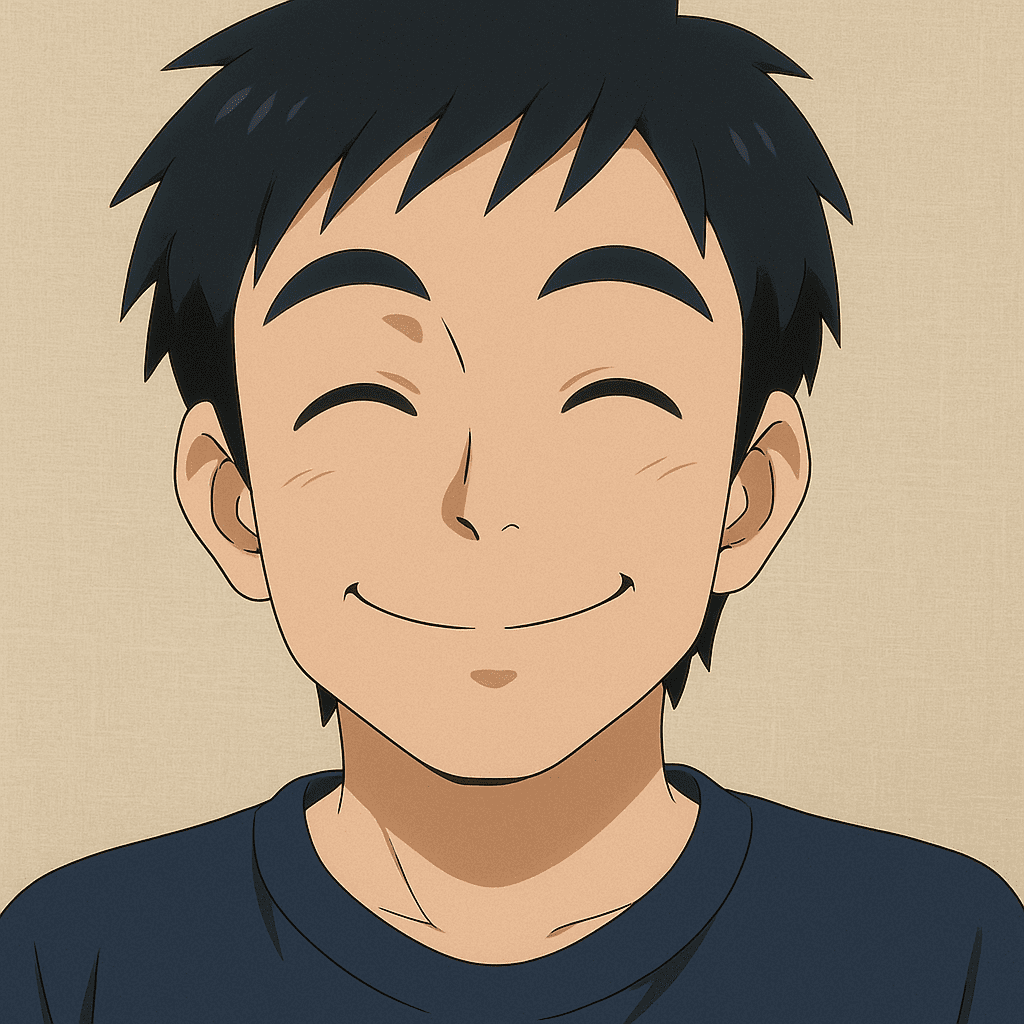 うどまる
うどまる1人でも多くの方が合格できるとうれしいです
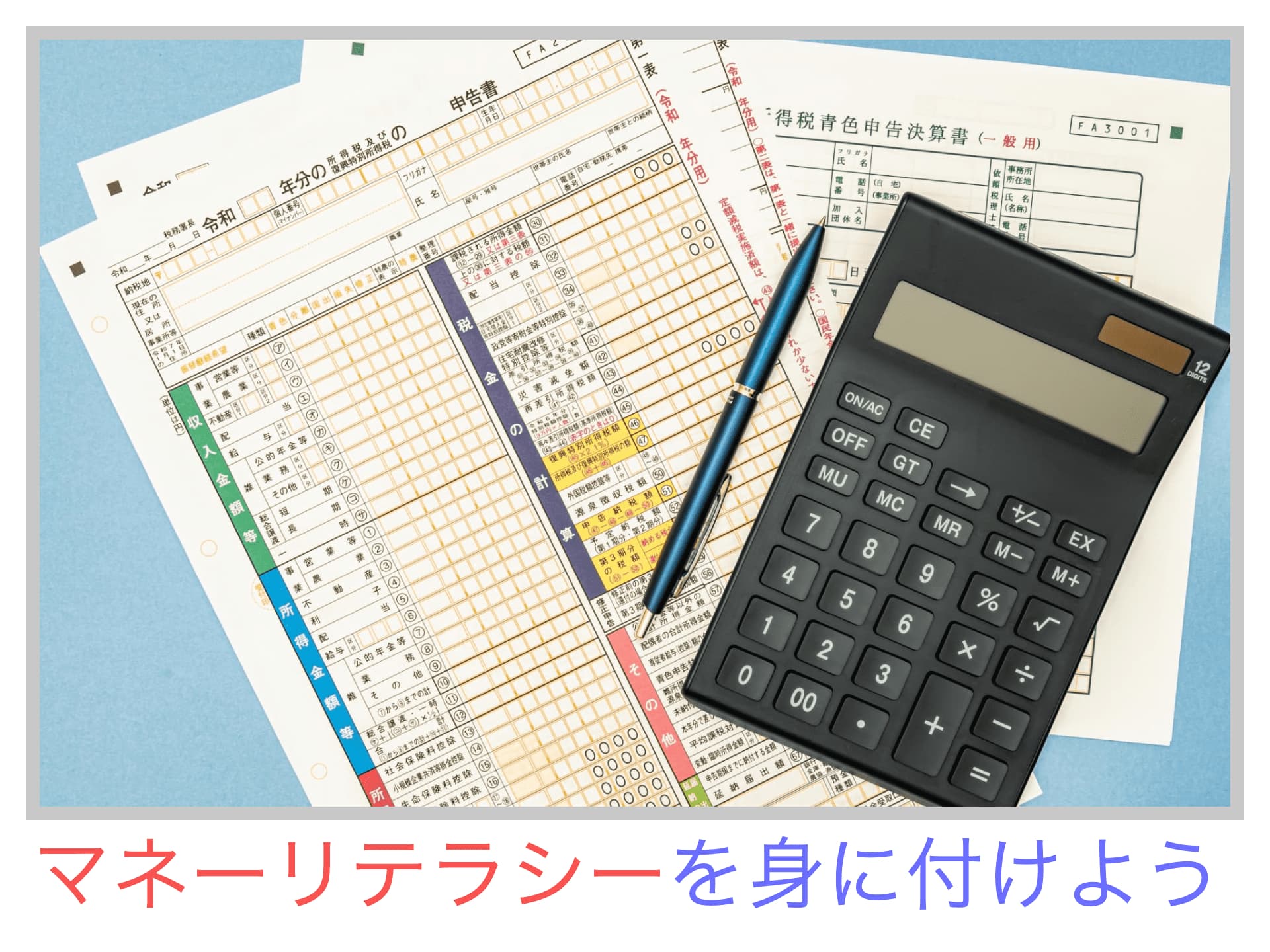
コメント